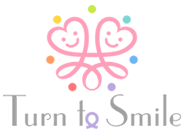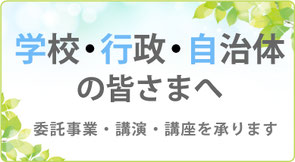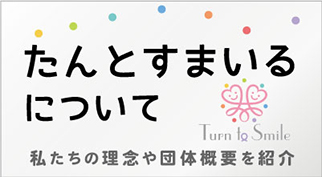暴力を手放すために、私は「相手をよく観て、相手の話を全身で聴くことを大事にしたい」と思っているものの、まだまだできていないことに気づきます。
私自身が元妻さんや子どもたちにしてきたDV・虐待の一つに「私自身の価値観を押し付けて、私自身の意見に従わせること」があります。これは、ランディ・バンクロフト氏の著書「DV・虐待加害者の実体を知る」の中の「変化へのステップ5」にも次のように書かれています。
「5.自分の支配的な行動のパターンと特権意識をひとつひとつ明らかにすることです。 自分がいつも使っていた虐待のやり方を詳細に語らなければなりません。それと同じくらい重要なことは、虐待を引き起こす元になっている信念と価値観に気づいて明らかにすることです。例えば、相手は自分に対して気を使うべきだとか、相手を自分より劣っていると見てバカにするとか、相手が何かしたことによって『暴力を振るわざるをえなかった』から自分には責任がないと主張するといったようなことです。」(*1)
(*1)「DV・虐待加害者の実体を知る」(ランディ・.バンクロフト氏著、明石書店発行)から引用
私の「自分の支配的な行動パターン」の一つは、例えば「返事をする、噓をつかない、相手の眼をみて話す」といった、いわば「自分だけの正しさ」を元妻さんや子どもたちに押し付け、約束として守らせたことです。そこには「正しいことだから押し付けてもよい」という価値観があり、それを私は特権意識として振りかざしていました。そして子どもが返事をしない、嘘をついたと言っては「約束を破った」として怒鳴ったり、叩いたりして私の言うことを聞かせようとしてDV・虐待を繰り返していました。
そのような暴力を捨てて、二度とDV・虐待をしないように、今はたんとすまいるでの学びを続けています。しかしそれでも、自分の信念と価値観によって、周囲の人を傷つけてしまうことがあります。例えば、職場での仕事。私は、自分の仕事の進め方をアドバイスだと思って周囲の同僚に伝えることがあります。しかし、同僚にとっては「聴きたい」と思わない限り、それは私の価値観の押し付けであり、特権意識の表れそのものです。アドバイスも、相手には暴力にしか感じないこともあると気づきます。
そうした特権意識をもって、私自身の歪んだ価値観を押し付けないために、私は「相手の話を聴く」ことが大切だと理解します。それは、いわば私が全身を耳にして相手の話を聴くことだと思います。しかし、職場では上司と部下、先輩と後輩といった上下関係が存在することも多く、それらを相手に意識させてしまうと相手の話を聴くことも難しいことがあります。それゆえ改めて、聴くことに加えて「相手を自分の鏡」として「相手をよく観ること」が必要だと思います。これらをアタマで理解しても実践することはなかなか難しいのが実情です。例えば仕事が思うように進まなかったり督促されると不機嫌になったりする私は、相手を観る前に「不機嫌な態度」を相手に押し付けてしまっていることもあります。すると、前述のようにまだまだ私は暴力を捨てられていないと思います。
それでもたんとすまいるでの学びを通じて、「変化へのステップ5 自分の支配的な行動のパターンと特権意識をひとつひとつ明らかにすること」に取り組んできました。そうしたパターンを「知って、理解する」ことから、改めて私は暴力を手放す行動を続けていくことができると思います。同時に、私のDV・虐待によって酷く傷つけてしまった元妻さんと子どもたちの痛み、悲しみ、苦しみ等を一つ一つ受け入れたいと思います。
そんな私は、「DV・虐待加害者の実体を知る」の中の「変化へのステップ6 自分が今やめようとしている虐待的な言動や考え方の代わりに、相手を尊重する言動がもっとできるようにすること」(*2)に取り組んでいきたいと思います。
2-10
(*2)「DV・虐待加害者の実体を知る」(ランディ・.バンクロフト氏著、明石書店発行)から引用