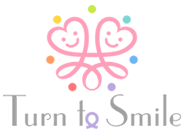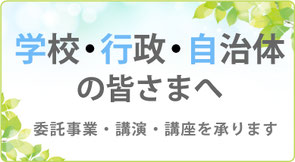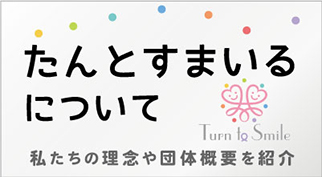グループでの学びは、多岐にわたる内容です。様々な角度から、私たちは自分の行動を見つめ直し、暴力に依存しない生き方を身につけることを目指しています。
その中でも毎年8月は特別です。8月は戦争を振り返る季節。原爆や終戦の日を意識する機会が多く、グループでも「戦争とDVの関連性」をテーマに映画やテレビ番組、本などに触れ、その気づきをまとめる課題が出されます。最初は「戦争と家庭内暴力?規模も違うし、どう関係があるのだろう」と正直ピンときませんでした。しかし学びを重ねる中で、両者の根底には驚くほど似た構造があることに気づかされました。
戦争とは、国家という巨大な権力が人々を支配し、従わせる仕組みの中で生まれます。兵士は「お国のため」という大義名分を与えられ、自らの命を差し出すことが当然とされました。疑問を抱くことは臆病者の烙印を押され、恥とされます。こうした空気の中で、多くの若者が自らの死を「誇り」だと信じ込まされました。そこには「支配する側に都合のいい価値観を植え付け、当たり前にさせる」という構造があります。
これはDVにも重なります。DV加害者は暴力を「しつけ」「愛情」「お前のため」という言葉で正当化し、相手を従わせようとします。被害者は暴力の合間に見せられる優しさにすがり、「この人は本当は優しい」と信じてしまう。そのうちに「自分が悪いから殴られるのだ」「逃げられない」と思い込むようになります。私自身、相手を傷つけたとき、その後で「でも自分は愛している」という言葉を口にし、自分の行為を正当化していたことがありました。戦争の教育が若者に「死を美徳」と思わせたのと同じように、DVもまた「支配を自然なもの」と錯覚させる仕組みを持っているのです。
さらに、戦争とDVの共通点は「暴力が心を縛る」という点にもあります。戦争では命令に従うことが習慣化され、疑問を差し挟む余地が奪われます。DVにおいても暴力と優しさの繰り返しが心理的な支配を強め、逃げる力を奪っていきます。どちらも身体的な痛み以上に、心を縛る効果を持っています。
私は中学1年の息子と一緒に、鹿児島県南九州市の知覧特攻平和会館を訪れたことがあります。戦争で散った若者たちの遺影や手紙を前に、息子はじっと立ち尽くしていました。展示を見終えた帰り際、息子が「自分とあまり変わらない年齢で死ななきゃいけなかったなんて信じられない」とつぶやいたのを覚えています。その言葉に私は考えさせられました。戦争が人の命をどれほど無理やり奪ったのか、そしてそれを「正しいこと」と思わせたのか。息子の素直な感覚を通じて、改めてその理不尽さが迫ってきました。
同時に、私はDVの加害者として、かつて自分がしてきたことと重ねざるを得ませんでした。暴力を「愛情の形」と言い訳し、相手を服従させようとしてきた自分。その姿は、国家が「お国のため」と言って若者に死を強いた構造とどこか似ているのではないか。大きな戦争と家庭内の暴力、一見関係のない二つの暴力の根底には「支配と正当化」という同じメカニズムが潜んでいるのだと気づかされました。
この気づきは、私にとって大きな意味を持ちました。戦争を遠い過去の出来事としてではなく、自分の加害性を見つめ直すきっかけとして捉える。DVを止めるためには、単に「手を出さない」と決意するだけでは足りません。相手を支配しようとする心や、それを正当化する思考そのものを根本から変えていく必要があるのです。
戦争とDVは規模も背景も違います。しかし「力を持つ者が正義や愛の名のもとに暴力を正当化し、弱い者を従わせる」という共通の構造を持っています。私たちが本当に暴力をなくすためには、その構造に気づき、自分自身の中の支配欲や正当化の癖を手放していくことが欠かせないのだと思います。
知覧で見た若者たちの笑顔の遺影と、DVの中で苦しんだ人々の姿。その両方を胸に刻みながら、私は「暴力を繰り返さない」という選択をこれからも続けていきたいと思います。
1-6