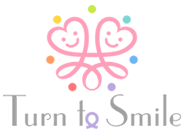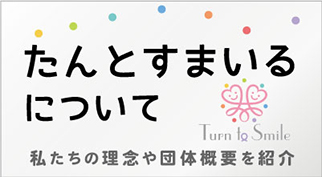「9年間の変化を振り返る」
(1)夫:40代(会社員、関東地方在住)
(2)妻:40代
(3)子:なし
(4)既婚or未婚:既婚
(5)同居or別居:同居
(6)プログラム参加期間:9年
1 パートナーとの出会いから自分がDVをするに至った経緯やその時の心情について
パートナーと出会ったのは2007年の1月。
2006年末にあるパーティで、とある男性と知り合い、演奏会に参加してみないか誘われた。たまには違う世界を見てみるのも悪くないと思ったので、参加してみることにしました。
その演奏会でいろんな人と話をしたのですが、最初に自分が座っている真正面にいたのが自分のパートナーとなる女性でした。
パートナーの第1印象は、かなり社交的に感じました。とにかくいろんな人と話をします。そんな彼女に関心を持った私は連絡先を交換して、時々メールをする仲になりました。
何度かメールのやりとりをするうちに、会いましょうという話になり、初めてのデートは映画を見ることになりました。
パートナーが、その時に自分の耳が聞こえにくいということに、トラウマがあること、それでかなり人から誤解されたり、虐めにあったりしたことをカミングアウトしてくれました。
私はそれを聞いて「人はそれぞれその人なりの勝手な価値観や考えで相手を見る癖があるからね。人によって相手を理解しようという気持ちがあるにしても完全に理解するのは難しいし、大半の人が自分の考えや価値観が無意識に正しいと思っているから」という話をしました。この時パートナーは「この人は普通の人とは違うかもしれない」と前向きに私のことを思ったそうです。
何度かデートをするうちに付き合う流れになったのですが、私が自己啓発のセミナーで多額の投資をしていること、また毎週講義を受けていることがバレました。
私はそのセミナーがどれだけ素晴らしいのかをパートナーに説明するのですが、パートナーは「セミナーがあなたにとって価値があるのは理解できるけど、多額のお金を払うのは世間一般的な価値観ではおかしい」とか「なぜ私とのデートよりもそっちの講義の方が大事なのか?」という話をしました。私は「パートナーだってピアノとか楽器でたくさんお金使っているでしょう?セミナーにお金がかかるのがどうしていけないのか?」とか「あなたのデートと私のセミナーを天秤にかけて比較することそのものがおかしいでしょう!?」と口論がエスカレートしていくばかり。
そして、ついにパートナーの反発に、彼女の頭に強烈な平手打ちをしてパートナーを泣かせてしまいました。
これが、私が認識するパートナーに対する最初のDVでした。
他にもパートナーのセミナーに対する否定的な言葉に私の怒りが噴火して、パートナーの弁当箱が入った荷物を道路上に叩き付けるという暴挙を働き、雨の中傘もささずに怒りをぶつけるように思い切り走ることしてみたり、パートナーから何か気に入らないことを言われると、頭に冷たいお茶をかけたり、暴言を吐いたり、怒鳴り散らしたりしていました。これらも今はDVと認識します。
しかし、パートナーか家族からのセミナーへの批判や、セミナー主催者側から「あなたの態度や行動が問題を作っている」などの冷たい態度から孤独と絶望を感じた私は、セミナーから一切手を切ることにし、それまで付き合っていたセミナー関係者の連絡先を削除することにしました。
それに伴い、パートナーと口論することは減り、DVも少なくなっていきました。
パートナーを心配させる問題がなくなったことで、平和な日々が続くものだとこの時は思っていました。
セミナーから離れて、パートナーと良好な関係性を作っていきます。やがて結婚を意識して、パートナーの自宅近くに二人で住めるアパートを借りて生活し始めます。
パートナーも週に2、3日遊びにくるような生活で、夕飯を作ってくれるのですが、時々焼き物を焦がしたり、電気の紐スイッチを壊してみたりと、見ていて不器用なところがあると感じました。
普段料理を含めた家事はお義母さん任せだとのことだったので、経験を積んでいけば、大丈夫だろうと思っていました。少し気になるのは細かいことにこだわりすぎて、なかなか物事が前に進まないこと。それで長い時間待たされることもしばしばでした。
待ち合わせ時間には90%遅れてきました。映画等決まった時間がある場合に遅刻されると、「せっかく時間決めたのに」という思いになってしまうことも時々ありました。
パートナーは外出前の準備で時間がかかり遅くなってしまうのが原因でパートナーも申し訳ないと思っていたようなので、私は常識がない人ではないのだなと思い、大目に見ていました。
いよいよ結婚することが決まり、両家への婚約の挨拶も終えて、結婚の準備を始めていくのですが、この時のパートナーの姿を見て、彼女に対して私が評価を勝手に下げていくことになるのです。
驚かされたのは、基本的に決められた期限を守らないということ。打合せ等の約束の時間に遅れてくること、特に結婚式前日に徹夜をして、当日衣装の着付けに2時間くらい遅れてきたことに呆れてしまいました。
もう1つは、一切の妥協を許さず理想ばかり追い求めすぎて、先のことを考えるという視点が欠けている女性だろうなと自分の決めつけを強化していきました。
こうして準備を行っていくにつれ、私の中で、パートナーを強烈に「パートナーはダメ女だ」だと決めつけました。
当時はそれほどそんなに決めつけをしているとは思っていませんでしたが、今考えると、この決めつけがDVをするきっかけの一つになった気がします。
しかし、この時は、結婚したらパートナーの考え方が少し変わると思っていたので、暴力的になることはありませんでした。
結婚式後、生活を始めていくわけですが、パートナーは家事に慣れていないのか何をやるにしても時間がかかる感じでした。特に掃除にはとても時間がかかり出かける時間に間に合わないこと等が度々ありました。
当時の私は時間を守ることにうるさかったので、パートナーの外出準備が遅いことにかなり文句を言ったりイライラしたりしていました。パートナーとしては早く出かけたい気持ちはあるけど、いろんな荷物を持っていきたいのかその準備がなかなか終わらないのでした。それとパートナーは整理整頓が苦手なところがあり、モノを捨てられず、どんどんためていくところがありました。そんなパートナーに私はイライラして、「整理整頓ができていないということは頭の中が整理できていないのと一緒」と言ってみたり、「ちゃんと考えて行動しているのかよ」と言ってみたり、「捨てられないというのは過去に執着しているからじゃないの?過去に執着して今を生きていないよね」と言ったりして、パートナーの行動を非難しました。パートナーは私の発言に反発することもありましたが、当時はあまり言い返してこなかったように記憶しています。
しかし、私が何度同じことを指摘しても同じことを繰り返しているように見えていたので、次第にパートナーとの関係性もぎくしゃくしていきました。パートナーから「あなたは賢いからできるのかもしれないけど、私にも色々事情があるからなかなか前に進まないの」とか「結婚式直後に罹患した病気でなかなか体が動かないこともあるのよ」とか「私のペースで準備させてよ」と言ってきました。私も最初は多少遅くなることは黙認していましたが、次第に1時間や2時間遅れるということが当たり前になってくると、またイライラして「いい加減にしろ!いつまで待たせるのだ!」「いくら自分のペースで準備したいってこれは遅すぎだろう!?」と感情的にパートナーを非難しました。時には、私のイライラがなかなか収まらず、外出時に、大声で文句を言ったり説教したりしていました。パートナーからは「人がいる前で説教されるのは恥ずかしいからやめてほしい」とか「そんな大声を出したら皆に聞かれるからやめてよ」と言ってきました。私は素直に従うこともありましたが、納得できない時は、「あなたが私の言うことを全然理解しようとしないから仕方なく大声出しているのではないか!?」と反論する、「周りの目なんて関係あるか!そんなことより俺の話をちゃんと聞けよ!」と怒鳴ったりすることもありました。
またこんなこともありました。外出前にパートナーの携帯電話に友人から電話がかかってきてそこから実に4時間も会話して私を待たました。パートナーが友人と電話が終わり、申し訳なさそうにしているところ、私は「今回は何も言わなかったけど、いかに自己管理、時間管理が全くできていないか分かったでしょう!?こういうのをほぼ毎日やって、私に度々迷惑かけているのだからね。いかに自分に学習能力がないのか自覚すべきだと思うよ」と皮肉と嫌味を言いました。今考えると、これは自分のDVを正当化していたと思います。
他にも、経済的なDVやパートナーの言葉や態度で気に入らないことがあると、イライラして怒鳴る、モノに当たる、パートナーの自転車の籠に「もう自宅に帰ってくるな!実家に帰りなさい」と大きな字で書いた紙を入れる等していました。
こうして行動を振り返ってみると、当時はいかに自分が正しいことをやっていて、パートナーは間違ったことをやっているのかにこだわっていました。またパートナーと自分との関係性は夫婦関係ではなく、親子/保護者被保護者の関係と思っていたので、自分が指導者/教育者となり、パートナーの教育指導を行う必要があると本気で思っていて、パートナーの気持ちや感情、立場を尊重しようという気持ちは希薄だったと感じます。
またパートナーへの決めつけがひどすぎました。不器用な人、期限を守らない人、頭が悪い人、嫌なものを嫌と言って努力しない人、お金の計算ができない人、余計な買い物をしてくる人、私のためになる話はせず無駄話が多い人。結婚前も結婚後も本当にダメな女だなと当時は決めつけていました。
そんなパートナーに対する不平不満を蓄積していく中で、更生プログラムに参加するきっかけとなるある事件が起きます。
2013年2月11日。この日は忘れもしません。
その日は、確か祝日でしたが、私が食器洗いをしたり、洗濯をしていたり、ごみ捨てをしたりしていました。パートナーは私の家事のやり方が、パートナーが考えていたことと違ったのか?食器洗いをしたら水切りをしてほしい、洗濯物を干すときはしわを取ってほしい、落ちたごみはちゃんと拾ってと言ってきました。今は素直に聞けるのですが、この時はパートナーに対するいろんな不平不満が溜まっていました。またこの時はパートナーからの「お願い」ではなく、「指図」と捉えていました。パートナーが持病で家事がしにくかったのだと思いますが、「パートナーは何もしないくせに口ばかり出してくる」と思っていました。そして、それらの鬱憤が溜まっていたものが爆発して、「口ばかりで指図してんじゃねー!!」と怒鳴り、座っていたパートナーの左肩を右脚で思いきり蹴り飛ばしました。蹴られたパートナーはその場に倒れたもののすぐに逃げましたが、その逃げているパートナーの後頭部を右手で思いきり平手打ちしました。この時の私は怒りの感情で身体がブルブル震えていて、「なぜ自分はこんなに怒りを爆発させているのだろう?」と思いながら、パートナーに対する怒りの感情をまだぶつけようとしつつも、我に返り何とか落ち着きを取り戻そうとしていました。
パートナーは当然かなりショックを受けていましたが、少し落ち着いて次のように話をしました。
「私が家事をちゃんとできていなくて負担をかけていたのは分かっているし、そのことに不満を持っていたのは分かった。だけど、暴力をふるうのは間違っている。私は自分がDVの被害者になってしまったことが悲しいし、結婚する前に暴力された時のことを思い出して辛い。」と涙を流しながら伝えてきました。
また、「もうこんな思いは二度としたくないので、今後どうしていきたいのか真剣に考えてほしい。暴力がいけないことだと分かっている?」と言われました。私が返答をせずにいると、「暴力がいけないって思えないなら一緒に暮らすのは難しい。そのことを含めて何か対策をしてください!」と言われました。
確かに、身体が震えるほどの怒りの感情はこれまでにない経験だったので、これは自分の何かがおかしいと思いました。何か対策をしないと自分が何をするか分からないという不安、恐怖がありました。一方でパートナーに対しては、暴力をふるってしまったことに対する罪悪感はあまりなく、むしろ口ばかり出して行動で示さないパートナーに対する不満が残っていて、「俺も悪いけど、パートナーも悪い」と反省する気持ちは薄かったように思います。
とはいえ、このままでは自分の人生が危ういものになってしまうと感じたので、インターネットでDV加害更生を行っているグループを調べてDV加害更生のみを専門でやっている団体で更生していく選択をすることにしたのです。
2 更生プログラムに参加した理由とそのときの心構えや不安、心配等について
最初に加害更生プログラムに電話したときに、事情を話したところ、「あなたのやっていることはDVです」と言われてショックを受けました。とにかく自分が変わらないことには何も始まらないし、自分の不安はなくならないと思っていた私は申し込みをして、更生プログラムを受けることにしました。
プログラムに参加する前に、3回面談を受けるのですが、その中でこれまで自分がやったDVにどんなものがあるのか?を知るため、あらゆるDV行為が記載されている紙を渡されて〇をつける、また該当しないものがあれば自由に記述する機会があります。これをやってみたのですが、いくつか該当するものはあるものの、あまり該当するものは少ないなと感じました。
1週間後にパートナーが書いたものを見せてもらいましたが、圧倒的ではないにせよ私が記載したものより多くの行為が書かれていました。私が記載せずパートナーが記載したものは私がすでに忘れていたことや中には身に覚えがないものもいくつか見られました。
代表者曰く、「あなたの場合は、あなたの記載内容とパートナーの記載内容でそんなに差はないけれども、一般的にDV経験者とDV加害者とで認識に大きな差があることは多いです。中にはDV経験者の記載内容が圧倒的に多すぎて、DV加害者が驚いて、俺はこんなことしていないと怒り出すケースもあります。これからプログラムに参加するにあたり、あなたが学びを深めれば、今あなたがここで書いた以上のDV行為に気付くこともあると思います。これからしっかり学んで、パートナーに心から謝罪して、あなた自身が変わってパートナーを尊重できる人間に変われるよう努力してください。」と言われました。
この話で、一筋縄ではいかないだろうな、ある程度時間はかかるだろうなとかなり身が引き締まる思いをしたことを今でも覚えています。
3 グループに対する期待、効果、挫折、疑問、懐疑等の率直な意見や感想
グループに参加していくつか気付いたことを書きます。
私がプログラム初回参加で、プログラムをやめてしまう人を見たので、当初は参加しているメンバーに「本当に変化する意志があるのか?」疑心暗鬼でした。実際に振り返りをしている参加者の話を聞いていて、本気で変化しようとしている人もいれば、「この人本気で変わる気あるのか?」と思う人もいました。ただ参加者が学びを生かせずDVをしてしまったことを振り返りする際は、他の参加者全員が真剣に話を聞き、何がいけなかったのか?どうしてそのようなことが起きてしまったのか?振り返りしてもらった内容が自分にも当てはまっていないか?心当たりがないか?と真剣に考えている姿を見てきました。本当は変わりたいと思っているのだけど、なかなか変わることができないジレンマを抱えているということに気付き始めました。振り返りをした参加者に対して、別の参加者が厳しい言葉をかけたり叱咤激励をしたりすることもありましたが、問題意識を持たせてくれるという意味で振り返りをすることはとても大切なことだと感じました。加害更生プログラムの代表者が「同じDV加害者同士がグループになって学びを深めていくことに意味がある。加害更生プログラムに参加して、変化できる一番の要因はプログラムのファシリテーターではなく、一緒に学んでいる仲間がいること、そして仲間が切磋琢磨していくことだ」と話をしてくれましたが、プログラムに長年通っていてそのことはつくづく感じることです。
その一方でグループに期待「しすぎない」ことも大切だと感じています。グループに参加していて学んでいる「気になっている」人や、DVをしてしまった参加者に対してとても良い忠告をするのに自分のDVのことになると全く学びを生かせない人もいます。
また、加害更生プログラムは、学びのためのツールをたくさん用意してくれたり、毎月書籍を読んで感想を書いたり、あるテーマで考えたりする宿題が出てくるので、たくさんの学びができること、そしてその学びを日常生活にも活用しようという気持ちに自然となります。
中でも、一番私に影響を与えたのは、「変化へのステップ」というDV加害者が変化するための段階を整理したものと「選択理論」という人間の行動のメカニズムを体系化したものでした。
「変化へのステップ」はDV加害者が変わる上で重要な内容を13項目に整理しているのですが、グループワークを行う際に必ず参加者で輪読します。どれも重要な内容なのですが、中でも重要な内容だと感じるのがその1番目「現在と過去のパートナーに対して精神的、性的そして身体的な暴力をふるってきたことを全部認めること」です。DV加害者は学びが浅いと、DVを矮小化・自己正当化してしまいがちです。それは自分のDVを認めたくない、自分が正しいと思いたいという考えから出発することもありますが、そもそも自分がパートナーに対する行為がDVであることに気付いていないこともあります。その気付いていないDVを含めて全部認めることだと思っています。だからこそ気付いていないDVに気付いて変えていくことが重要です。グループワークを通して日常生活の自分の言葉や行動に対して「自分の今の行動や言葉は本当に良かったのか?間違っていなかったのか?」という疑問を自身に向けることで、自分のDVに気付くようになり、やがて変化することを実感できるようになると感じます。
選択理論で重要だと感じるものが「外的コントロール」と「内的動機付け」との違いです。外的コントロールとは、自分が相手を変えられる、相手も自分を変えられるという考え方のことです。典型的なものとしては、親が子供によく「親の言うことを聞きなさい」とか「何でお母さん(お父さん)の言うことを聞かないの!」と怒鳴りつけたり、叱ったりするのを見かけます。また上司が部下に「何でお前はこんなこともできないのだ」とか「俺の言うとおりにやっていればこんな失敗しなかったのに」と𠮟りつけるシーンを見たことがある人も多いのではないでしょうか?
親が子供に、上司が部下に命令や指図をされて素直に喜んで行動する人がどれくらいいるでしょうか?現代社会でこのようなことがあまりにも当たり前のように起きているのでイメージがしづらいかもしれませんが、外的コントロール下で人が喜んで楽しんで行動するケースはありません。選択理論は外的コントロールはやめて、内的動機付けから行動することを基本としています。「他人は変えられない。変えられるのは自分だけ」ということです。
この思考に変えるためには「自分の行動や言葉にすべて自分が責任を取る」ことが必要になりますが、「他人の行動や言葉に自分が責任を取る必要性はない」ということにもなります。
内的動機付けを意識するようになってから、パートナーへのDVが激減したばかりでなく、パートナーとの関係性が飛躍的に改善しました。自分の機嫌を自分で取らなければいけないこともあり、大変なこともありましたが、それも自分の変化へのステップとして捉えて今ではとても幸せな気持ちで過ごせています。
世間では「DV加害者は変わらない」と言っている方も少なからずいるようですし、DV加害者の罰をもっと厳しくするべきという論調もあるようです。ニュースで報道されているDVから派生した児童虐待殺人事件やDVによる殺人事件が起きているという厳しい現実もあるので、DV加害者は変わらないと思いたい気持ちも理解できます。ただそれでは、DV加害者は減ってはいかないし、社会も変わらないと思います。DVは自分には関係ないと思っている方は多いと思いますが、環境と状況がそろえばDV加害者、経験者はいつだれがなってもおかしくないと感じています。
DVのない社会を実現するためには、DV経験者の保護の視点はとても重要ですが、DV加害更生もそれと同じくらい重要なものだと自分は感じています。これからもDVをしてしまった人間として変化し続け、パートナーは勿論のこと社会全体の安心に貢献できればと考えています。
4 グループで学んだことによる気づきや変化
グループで学んだことによる気付きや変化について、3つご紹介したいと思います。
1 パートナーの感情的な不満や不快感をどう捉えなおすのか?
私がプログラムに通い始めて最初に頭を悩ませていたのが、パートナーが私に対して感情的に不満や不快感を言葉に出すと、私への「文句」「攻撃」「強制」と捉えてしまうこと、それに対して反発心で、怒鳴り散らす、モノに当たる、不機嫌になる、黙り込んで怖がらせる等のDVをしていたことでした。グループでこのことを振り返りで話した時、「パートナーがあなたを攻撃した/文句を言ってきたと言っているけど、それって本当に攻撃や文句なのか?」と仲間に質問されてハッとしました。
パートナーからも「私は不平不満や不快感をアウトプットしているけど、あなたを攻撃したり、責めたりしているつもりはない」と言われていました。しかし、当時の私は「いや、お前は絶対俺に文句を言ったり責めたりしている!そうでなければ不平不満や文句、不快感を夫である俺に言うはずはない!」と決めつけていました。結婚前に私が自己啓発セミナーに参加していて、そのことでかなり反発されていて「パートナーは不平不満があれば、必ず攻撃したり責めてきたりするはずだ」と強烈に思い込んでいました。パートナーに責めていない、攻撃していないと言われてもなかなか信じられずにいたのです。しかし、不思議なものでパートナー以外の人に疑問を投げかけられて「パートナー以外の人から同じことを言われたということは自分の考え方に何か問題があるのかもしれない」と思えました。
それから、パートナーが私に対して感情的に不満や不快感を言葉に出す時に、私が「文句」「攻撃」「強制」と捉えず「パートナーは自分の不平不満や不快感を表現しているだけだ」という価値観に変えるように、自分の気持ちを鎮めて冷静になるように「パートナーは自分の不平不満や不快感を表現しているだけだ」とつぶやいてみる等行動に移しました。
不平不満や不快感は聴いていてあまり気分がよいものではないため、最初はうまくいきませんでしたが、徐々にパートナーの感情的な言葉に対して過剰反応しないようになりました。
ただそれでも心のどこかにしこりが残っている感じがしました。そこで私が考えたのは、「そもそもパートナーの感情的な言葉にどうして過剰反応してしまうのか?」ということでした。
それを紐解いているうちに、自分が幼少期に母親からネチネチ不平不満を言われていたことに対してすごく不愉快な思いをしていたことを思い出しました。幼少期の頃の私は母親から「呑気だから」と否定的に言われてとても傷つきました。「そして呑気はいけないことなのだ」と思い込み、何事も一生懸命やるようになりました。
そして努力している姿を見て父親は褒めてくれていたのですが、母親はあまり褒めることはなく、一生懸命やっていない私、努力していない私を発見するとネチネチ言ってくるのでした。その「ネチネチ」言う母の姿とパートナーの「感情的な言葉」を重ねていました。そして母がネチネチ言っていたことに対して、幼少期の私は「こんなに頑張っているのになぜそこまで言われなきゃいけないのだ!?」「どうしたらいいのだ!?」と心の奥底では不満やストレスを溜めていたのでした。パートナーに感情的な言葉を言われた時も「別に自分はそんなに悪いことをしていないのになぜそんなに不平不満や不快感を言われなきゃいけないのだ!?」「不平不満を言われるのは俺のせいなのかよ!俺に責任をなすりつけるな!」という考えで感情が起きていることに気付きました。そして、自分の幼少期の傷付きを自分の中でヒーリングするとともに、自分の考え感情をスムーズに切り替えることができるようになりました。
パートナーの感情的な言葉に対して過剰反応しなくなったのは、選択理論を学んだことも大きいと感じます。このケースでは「パートナーが感情的になっているのは私を変化させようとするためではない。パートナーは単純に感情を表現したいだけで、私にはただ聞いて受け止めてほしいだけ。もしパートナーが私を変えようとしたとしても、パートナーに私を変える権限はないと伝えればよい」という捉えなおすことができます。私が変えられるのは私だけ、パートナーを変えられるのはパートナーだけということです。私がパートナーにできることは、パートナーが変わりたいと思ったときにパートナーを信頼して支援することだけです。このように考えられるようになってから自分の心が軽くなったと感じています。
2 「口で言ってもわからない人間は実力行使で体に分からせる。」という価値観を変える
次に気付いたことは、「口で言っても分からない人間は、実力行使で体に分からせてもいい」という価値観でした。今考えると恐ろしい価値観を持っていたと思うのですが、パートナーにDVをしていた時、暴力をしてはいけないと心から思っていませんでした。その原因がこの価値観にありました。
この価値観をどこで身につけてしまったのか?を考えたときに父親の躾という名の脅迫と学校の指導を思い出しました。父親は自分の気に入らないことや悪いことが起こると、「夜中に庭に出すぞ!」と言ったり、「もみあげを上に引っ張るぞ」と言ったりしていました。その時の私は「人が自分の言うとおりにしなかった場合や相手が間違った行為をした場合は、罰してもよい」という価値観を覚えたのだと思います。
また学校、特に中学、高校は暴力がひどく、中学校で研修旅行に行った際に校則違反をした生徒を集めて教師が一人一人にビンタを食らわせるとか、夜寝ている時にふざけていると廊下に出されて正座をさせられるとか、ホームルームで規則違反をした生徒を立たせて書類をバン!と叩きながら怒鳴る、廊下で小言を言った生徒に教師が胸倉をつかんで怒鳴る等、身体的な暴力、言葉の暴力、精神的な暴力が当たり前にありました。そして、それは「躾」とされて、「間違ったことをした生徒が悪い」「生徒が間違ったことをしたので教師が怒るのは当然だ」という土壌を生んでいたように思います。
実際に、私がパートナーにDVをしていた時も、ほとんどの場合「躾」のつもりでした。「そんな考え方だから何をやってもうまくいかないのだ」「本当に必要なことをやればいいのに余計なことが気になっていろんなところに目移りするから先に進まないのだよ」等言及して自分の言うとおりに動かないと、さらに激しく責め立てるという繰り返しでした。
このような価値観に気付いたことと、選択理論で言う「自分が変えられるのは自分だけ」ということを学んでから、「躾」と称して相手を責めたり、相手の悪いところを指摘したり、改善提案や助言をしたりすることは徐々になくなっていきました。今は「パートナーはパートナーのペースがあるだろうし、パートナーにもパートナーなりの考えがあって行動していることだろうから」と考えて見守るか、自分が別のことをしてパートナーを支援します。改善提案や助言をするのはパートナーからリクエストがあったときのみ。そうすることで、パートナーの動きや考えをしっかり観察できるようになり、パートナーも一生懸命やっているのだと気付けるようになり、尊敬もできるようになったと感じています。
3 努力しなければ自分は認められない。
最後に自分が数年前にパートナーに対して大きな身体的暴力を犯してしまい、警察に傷害罪で逮捕される寸前まで行った時の話をします。
その当時の私はパートナーの持病による症状でパートナーの言葉や行動に振り回されていました。それでも私はパートナーにDVをしてしまったという負い目や償いの気持ちがあったので、何とか踏ん張っていました。しかし、次第に体力的にも精神的にも消耗してしまい、「何とかならないか?」という話をしたところ、パートナーが感情的に訴えてきました。あまりにも激高しているように見えたパートナーに対して、「どうして俺はこんなに一生懸命やっているのに責められなければならないのか?」という強烈な怒りの感情が沸いて、パートナーに「この野郎!」と怒鳴りつけて、パートナーに身体的暴力をしました。自分の拳の痛みに我に返って「とんでもないことをした」と感じて、暴力が止まりました。
パートナーから「苦しかったのだろうけど、暴力はダメ。プログラムで今日起きたことを話して」と言われました。
このことを受けて、更生する以外に道はないと思い、今回のDVがどうして起きてしまったのか?をしっかり時間をかけて明らかにしていきました。その中で気付いたことは自分では背負いきれないもの、背負う必要がないものまで引き受けてしまったと気付きました。そして、その裏には「自分は努力しなければ世間に認められない」「ありのままの自分は否定されてしまう」という強烈な思い込みがありました。それが「自分も他人も誰も信じられない」という非常に歪んだ価値観につながっていました。本当は「自分のことを信じたい、他の人のことも信じたい」があるので、私が必死に努力している姿をパートナーに認めてほしいという思いがどこかにあったのだと思います。
それからは、パートナーの気持ちやリクエストを大切にしつつ、自分のことを大切にするという習慣を身につけるようにしました。パートナーからのリクエストで無理がありそうなものは柔らかく断ったり、後に回してもらったりしました。
それ以来身体的な暴力は一切しなくなりましたし、暴力をする必要性を感じなくなりましたし、もう二度と暴力をしたくないと思うようになりました。
5 DVを繰り返さないために今現在取り組んでいること
DVを繰り返さないために今現在取り組んでいるものは特にこれというものはないですが、いくつか気付いたことを書きたいと思います。
一つ目は「自分の機嫌は自分で取る」ということを心がけています。自分が様々な環境や状況でどんなアイデンティティ、イメージ、感情、考え、言葉、行動するか?は全て自分次第であり責任を持つという意識があります。
責任と言うとすごく重たいように感じるかもしれません。実際責任を持つというのは勇気、決断、忍耐が必要なケースもありますが、一旦「責任を持つ」と決断すると、自分の軸がしっかり立つ感じになり、覚悟というか「自分がやるしかない」というエネルギーが沸いたりします。それが自分の変化につながり「面白いな」と感じることがありますし、楽しめる側面もあるのを感じています。また不満を感じたり、不機嫌になったりした時に「どうしてそうなったのか?」を振り返ることがあります。そうすることで、自分の行動にどんな課題があるのか?が見えたりすることがあります。私の場合、行動が義務感から出発してしまうことが多いので、そもそも自分がどうしたいのかの視点が抜け落ちてしまうことがあります。そこで不満や不快感、不機嫌になるときは「義務感で行動していないか」を自問自答したりしています。
二つ目は「自分の考え方を絶対視しない。相手の意見を取り入れてみる」ことを心がけています。以前の私はパートナーに対して、自分の常識や当たり前を押し付けていました。例えば「時間を守る」ことや「自分で間違ったりミスしたりしたら自分で落とし前をつける」等の価値観がかなり強烈でそれが守れないパートナーを責めていました。パートナーも最初のうちは謝っていましたが、私があまりにもうるさく言うので「そこまでなぜ言われなきゃいけないの?」とか「別に仕事じゃないのだからフォローしてくれたっていいじゃない」と言ってきましたが、そんなパートナーに私は「だから周りから大丈夫か?と言われるのだ」とか「そんなの自立した大人とは言えない」とさらに反発していました。
今は、こうした自分の考えを絶対視して自分の価値観を押し付けることが一切なくなりました。むしろパートナーのリクエストや提案を聞いて、それをどうしたら実現できるか?とか落としどころはどこだろうか?と考えられるようになり、その方が楽しいことを学ぶことができました。パートナーがミスをしたり間違ったりした場合でも、それをどうしたらリカバーできるのかとか、どうしたらパートナーの心の傷を癒すことができるのか等を考えるようにしています。
三つ目は、「いろんなモノの見方、考え方に触れて、自分が変化し続けること、また周りの変化にも貢献していく」ということを心がけています。今はDV加害更生プログラム以外にも、オンラインイベントやセミナーに参加してみたり、DV加害更生プログラムの説明会で体験談をお話しさせていただいたり、新聞や雑誌、ネット等でDVや暴力の記事を読んで必要な場合は仲間に共有したりしています。DV加害更生プログラムでの学びは勿論大切ですが、社会で起きていることに目を向けたり、DVが起きる背景や過去の経験を取り入れたりすることも大切だと思っています。なぜならば、自分たちのDVは自分で選択したものとはいえ、その選択の根拠となっているものは家庭環境、地域社会の通説、常識、歴史に密接に関係していると思っているからです。自分と社会がどうつながっているのかを学ぶことは社会に対する自分のあり方をどう変化させるのかに役立つと考えています。
6 学んだことでパートナーに対して思うこと、関係性の変化等
結婚した当初は、無意識にパートナーをバカにしたり、見下したりしていました。それは自分の目から見てパートナーが知識や知恵がなく未熟で不器用な存在に見えたからだと思います。DV加害更生プログラムでは、DVを「力と支配の関係」と見ますが、学びをする前の自分は無意識ではありましたが、まさにパートナーを力で押さえつけて支配しようとしていたと思います。
学んだことを通して、いかに自分がパートナーに対して酷い決めつけをしていたのか?またネガティブな部分しか見なかったのかに気付けました。そしてそれがパートナーの尊厳を破壊する行為だったのだとも気付けました。
今は、こんなDVをしてしまった私の変化をずっと忍耐強く待ち続けてくれたことに寛大さと尊敬、感謝を感じずにはいられませんし、私のことを心の底から信頼してくれる唯一無二の人だと感じます。そんなパートナーとの関係にDVは必要ないと強く感じていますし、パートナーの人生を心の底から応援したいと感じています。
今パートナーとは仲良く暮らしており、毎日の生活がとても楽しいです。そんな日々がずっと継続できるようにこれからも自分の変化を通して関係性をより良いものに変化させていきたいと思っています。
一般社団法人 Turn to Smile たんとすまいる
東京都港区浜松町2-2-15 浜松町ダイヤビル2F
MAIL:info@turn-to-smile.org
平日: 10:00~18:00
(面談時間 月・木・金:20:00)
土日祭日: お休み
※面談中のために応答出来ない場合がございます。
その場合は、お手数ですが改めてご連絡お願いいたします。